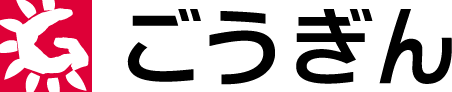背景・課題
- デジタルな銀行への変革を目指し、AIなどの最先端デジタル技術を積極的に取り入れ、サービス向上や営業スタイルの変革に積極的に取り組む
- AIとITを組織に組み込み、人は付加価値の高い業務に専念するハイブリッドな組織の実現を目指している
- 担当者の経験の有無などによって、アウトプットの品質や所要時間にばらつきがあった
Smart Generative Chat導入の決め手
- 閉域で利用でき、セキュリティ面の懸念なく使えるChatGPTシステムを短期間で構築
- ファイル読み込みやRAGなどの機能が豊富
- リモートだけではなくオンサイトの保守にも柔軟に対応
Smart Generative Chat活用内容
- 文書作成・校正、翻訳、アイデア出しや情報収集・論点整理、プログラミングコードやエクセル数式作成支援などに幅広く活用
- RAGを用いて社内規程等を学習させ、人の代わりにBotが問い合わせに回答
効果
- 経験が浅い人でもテンプレートやシナリオの活用により外部環境分析や調査業務を短縮、さらにアウトプットの標準化に効果が出ている
- よりセキュアな環境で利用ができるため、業務活用の幅が広がっている
- 従来のシステムに抵抗感があったユーザーにも受け入れられやすく、より多くのユーザーがSmart Generative Chatを活用できるようになった
背景・課題
デジタルな銀行への変革を目指し、生成AIを組織に組み込むことで人は付加価値の高い業務に専念する
Q.
まずは貴社のIT戦略や生成AIに関する意識について教えてください。
A.
2024年から始まった新中期経営計画では、デジタルな銀行への変革を目指し、AIなどの最先端デジタル技術を積極的に取り入れています。これにより、お客様サービスの向上と、お客様との接点である営業スタイルの変革に積極的に取り組んでいます。そのためにはAIとITを組織に組み込み、人は付加価値の高い業務に専念するハイブリッドな組織の実現を目指しています。
AIや生成AIといった最新技術に対しては、当行の経営陣は非常に関心が高く、活用したいという強い意思を持っているので、取り組みを全行的に進める体制を整えています。
Q.
生成AI導入以前にあった課題を教えてください
A.
取り組み以前は、担当者の経験の有無などによって、アウトプットの品質や同じ業務でも必要な時間にばらつきがありました。例えば、近年当行で力を入れているコンサル業務ではお客様の外部環境等の分析を行うことがありますが、ベテランでは長年の経験から容易にできても、経験が浅い担当は何日間もかかることがありました。
Smart Generative Chat導入の決め手
閉域で利用できセキュリティ面の懸念なく使えるChatGPTシステムを短期間で構築
Q.
生成AIの導入にあたって調査検討時に重点を置いたポイントはありますか。
A.
今回の開発にあたっては閉域網で利用できることが大前提でした。Smart Generative Chatの前に利用していたSaaS型の生成AIサービスでは、融資情報をはじめとした機密情報の取り扱いを制限していましたが、閉域のSmart Generative Chatであれば行内環境と同様に利用できます。また、ファイル読み込みやRAGの機能が充実していることを重点項目とし、検討を進めました。
Q.
Smart Generative Chat導入の決め手となったポイントを教えてください。
A.
なんといっても閉域で利用できるChatGPTシステムを短期間で構築できることです。閉域での構築に対応できるシステム会社様が少なく、この点を探すのは苦労しました。システムサポート様は以前より当行開発に携わっていただいたこともあり、提案から開発までスピーディーで、構築自体は2週間程度で対応いただきました。また、当行の場合、当行拠点での保守が必要となるため、保守がオンサイトでも柔軟に対応いただける点もポイントでした。
Smart Generative Chat活用内容
文書作成・校正、翻訳、アイデア出しや情報収集・論点整理、プログラミングコードやエクセル数式作成支援などに幅広く活用
Q.
Smart Generative Chatの主な使用用途を教えてください。
A.
多岐にわたり利用しています。文書作成・校正、誤字脱字チェック、英文契約書の翻訳、アイデア出しや情報収集・論点整理、プログラミングコードの支援やエクセル数式作成支援などです。
Q.
導入時に閉域網であることを重視されたとのことですが、閉域網ならではの使い方はされていますか。
A.
RAGを積極的に利用しています。行内の規程やマニュアル、FAQなどを 学習させ、人の代わりにBotが問い合わせに回答できるようにしました。またSmart Generative Chat導入前に利用していたSaaSでは「この情報はチャットに入力してよいのか?」と都度確認が必要でしたが、閉域網ではそういった判断も不要であり、融資情報をはじめとした機密情報も扱えることから各段に利用の幅が広がったと考えます。
Q.
Smart Generative Chatの優れていると感じる部分はどこですか。
A.
まずは会話形式で生成AIが手軽に使えるインターフェース、テンプレートやシナリオやボットといった機能が豊富であること、またRAGについてもいくつかの検索方式を選べ、チャンク分けも管理者画面から分割単位の指定が可能など、RAG回答精度向上のためのさまざまな方法が用意されていることです。これらは他のサービスを比較してもなかなかないのではと思っています。またコスト面も他社様と比べ導入しやすい価格であるのと、料金プランが利用者数に応じたユーザー課金ではないため、全員に利用を呼び掛けられるというメリットがあります。
Q.
Smart Generative Chatの全社的な展開にあたり考慮したことや事前・事後に取り組まれたことがあれば教えてください
A.
当行では2023年6月よりSaaSの生成AIサービスを利用し、1年で利用者を600名弱まで伸ばしました。並行して定期的な勉強会の開催やユースケースの共有、使えるプロンプトの開発を行ったりしました。生成AIに対する一定のリテラシーやスキルの土壌ができていたこともあり、抵抗感なく今回の移行に進めるように準備をしました。また、導入の際には行内周知も行いましたがまだまだ不十分だと感じておりますので、この部分は力を入れていきたいと考えています。
Q.
ご利用者さま(ユーザーさま)からはどのような声があがっていますか
A.
「インターフェースがかっこいい」「手軽に使える」といった声をもらっています。チャットベースで使えるので、従来のシステムに抵抗感があった方にとってもハードルが低いのかもしれません。他にも、行内環境で利用できるようになったため、より使えるシーンが増え、これまでChatGPTシステムを利用していただいていない方にも多く使っていただいています。
効果
業務品質や効率のばらつきが減少し、特に若手を中心に分析・調査業務で大幅に時間短縮
Q.
Smart Generative Chatの導入で感じている効果を教えてください
A.
経験の浅い人でもこれまでより早く業務が完了することができるようになったり、品質のばらつきが薄まってきたりしていると感じます。例えば当行が最近力を入れているコンサル業務では、テンプレートやシナリオの活用により外部環境分析のアイデア出しで業務効率化の効果が出ています。他にも、これまで時間がかかっていた調査業務が大幅に短縮できた例もあります。特に若い行員にとっての効果が顕著で、これまで長時間かかっていた業界に関する外部環境分析などが、短時間で終了したという声が聞かれました。具体の削減効果は現在集計中ですが、引き続きユースケースを増やし、さらなる業務効率化を目指していきます。
Q.
全社的な展開ののちに見えた課題や現在も抱えている課題があれば教えてください。
A.
まずは、利用者を広めることと、生成AIを活用する上でのスキルや研修がもっと必要だと感じております。さらに利用を推進していくために行内での発信やユースケースやプロンプトの共有などに力を入れていきたいと考えています。
Q.
貴社の生成AIに関する今後の取り組みについて、計画があれば教えてください。また、その将来に向けて、システムサポートにどのようなことを期待しますか
A.
今後当行では生成AIを業務に組み込み、生成AIを意識せずとも利用できる環境を構築することを目指しています。また行内利用促進のためアイデアソンの開催も検討しています。システムサポート様には今後のSmart Generative Chatの機能追加はもちろん、他のユーザー企業様とプロンプトなどの事例を共有する仕組みづくりをしていただけると助かります。また今回の導入をきっかけに、既存システムの連携なども一緒に検討できると幸いです。