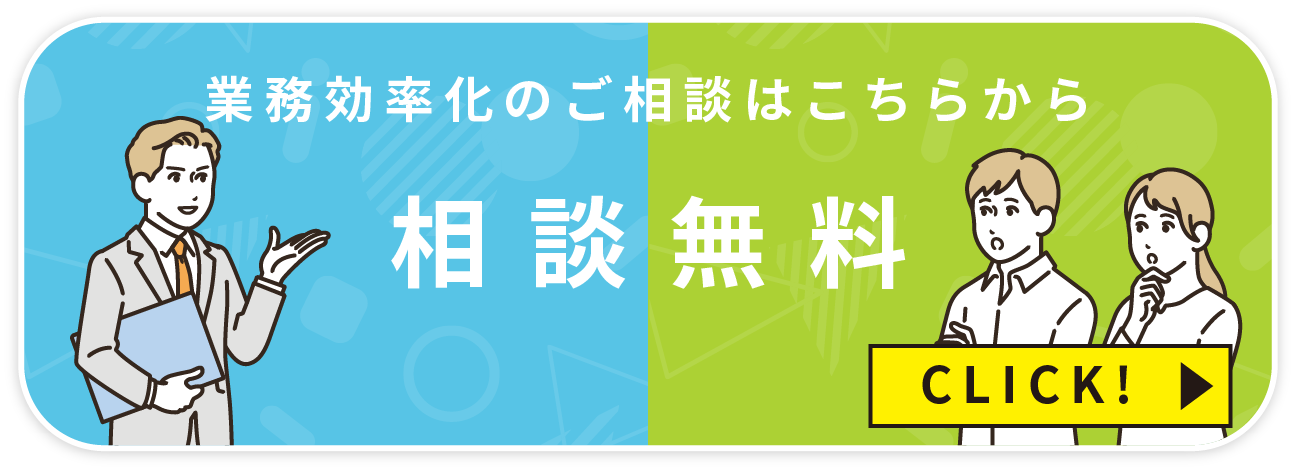2026年は、街角にヒューマノイドロボットが溢れる年ではありません。むしろ、クラウド上のエージェントAIが複数メーカーのロボット身体を横断的に操るための「物理レイヤー」が立ち上がる、静かな転換点となるでしょう。富士通が2025年12月に発表した「Kozuchi Physical AI 1.0」は、まさにその物理レイヤーの標準ポジションを狙う日本発の技術です。本稿では、この技術が切り開く未来の輪郭を、世界の動向とともに描き出します。
Physical AIレイヤーへのパラダイムシフト
NVIDIAが定義する「Physical AI」の本質
NVIDIAは公式グロッサリで、Physical AIを「現実世界で知覚・推論・行動するAIシステムの総称」と定義しています[1]。ここで注目すべきは、特定のロボット製品ではなく、3Dシミュレーション、合成データ生成、強化学習、大規模モデルを統合した「開発から運用までの一体型スタック」を指している点です。つまりNVIDIAが描くのは、複数のロボットや自律マシンをまたいで動く「物理空間のOS」のような存在なのです。
さらに同社は2025年のプレスリリースで、Omniverseを基盤に工場デジタルツインとヒューマノイドを含むロボットを接続し、製造業の再工業化を進める構想を明らかにしました[2]。ここで描かれているのは、単一メーカーの製品ではなく、国家レベルのPhysical AIインフラです。世界のトップランナーは既に、ロボット本体の差別化競争から、それらを束ねる抽象レイヤーの覇権争いへとシフトしているのです。
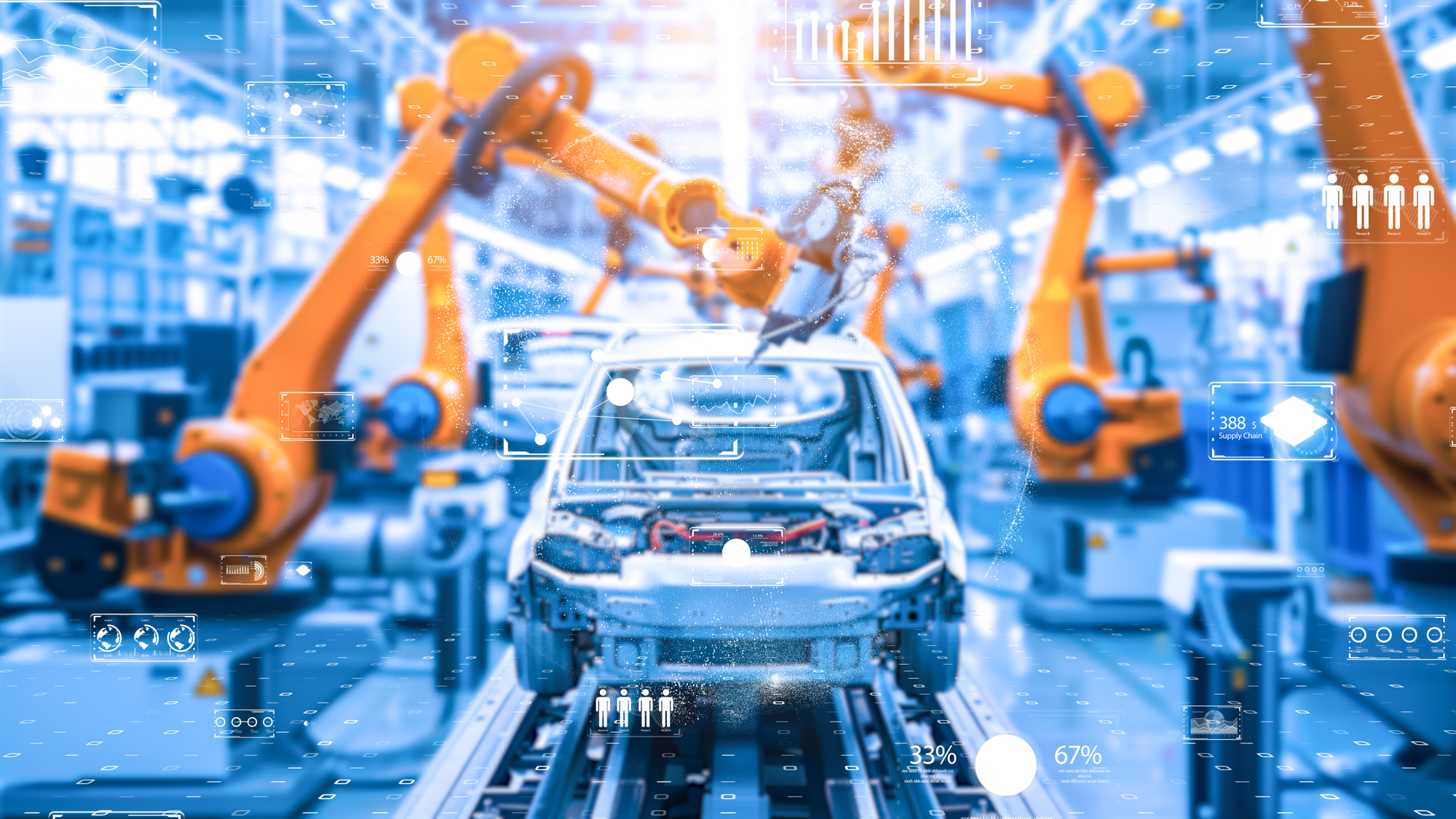
産業界が向かう統合プラットフォーム戦略
Accentureは2025年4月、Schaefflerと共同で産業用ヒューマノイドの実装に向け、NVIDIA OmniverseとMicrosoft技術を活用する取り組みを発表しました[3]。この事例でも、主役は単一機体ではなく「工場全体のデジタルツインと複数ロボットをつなぐ物理AI+クラウドレイヤー」です。Accenture自身が「physical AIとロボティクスで産業オートメーションを再発明する」と表現しているように、焦点はシステム全体の最適化にあります。
これらの動きから明らかなのは、価値の源泉が「ロボット身体の性能」から「異種ロボットを束ねるPhysical AI統合レイヤー」へと移行しつつあることです。2026年のヒューマノイド元年とは、この中間レイヤーが本格的に立ち上がる年として捉えるべきでしょう。
富士通Physical AI 1.0が担う役割
エージェントAIと物理世界をつなぐ翻訳者
富士通は2025年12月24日、「Fujitsu Kozuchi Physical AI 1.0」を発表しました[4]。同社はこの技術を「Physical AIとエージェントAIをシームレスに統合する新技術」と位置づけ、2025年10月に発表したNVIDIAとの戦略的協業における最初の成果であると説明しています。重要なのは、これが特定ロボットの製品ではなく、NVIDIAのソフトウェアスタックと富士通独自技術を統合した「システム全体を束ねる技術」である点です。
富士通のコーポレートブログ「Predictions 2026」では、Physical AIがエージェントAIとエッジで動作可能な小型AIモデルの発展によってさらに活用が進むと予測されています[5]。つまりPhysical AI 1.0は、クラウド側の知能(エージェントAI)と現場側の実行力(ロボット身体)、そしてエッジの判断力(小型モデル)という三層構造を前提に設計されているのです。

日本発の「身体スイッチングOS」という可能性
Physical AI 1.0の本質は、NVIDIAのグローバルスタックに日本の産業固有要件を統合し、クラウド上のエージェントAIが複数メーカー・複数形態のロボット身体をほぼ同じインターフェースで扱えるようにする「身体スイッチングOS」だと解釈できます。この構想が成功すれば、現場の意思決定は「どのメーカーのロボットを導入するか」から「どの業務フローをPhysical AIレイヤーに登録すれば、どの工場でも再利用できるか」へと変わるでしょう。
「1.0」というネーミングも示唆的です。これは単発のユースケース実装ではなく、繰り返し拡張されるプラットフォームとして構想されている可能性が高いのです。富士通は日本の現場知と世界標準のAIスタックを結びつける「翻訳レイヤー」を、日本企業自身が握れるかどうかの試金石を打ち出したと言えるでしょう。
2026年を分水嶺とする市場構造の変化
数十億体時代を見据えた投資競争
Goldman Sachsは2024年のレポートで、ヒューマノイドロボット市場が2035年までに少なくとも60億ドル規模に到達すると試算しました[6]。一方、世界経済フォーラムは2040年までに数十億体のヒューマノイドが稼働する可能性を指摘し、中国市場だけでも2024年の27.6億元(約3.8億ドル)から2029年に750億元(約102.6億ドル)へと急拡大すると予測しています[7]。
これらの数字が示すのは、ヒューマノイドそのものには巨額の資金が流れ込み始めているものの、まだ本格普及の前夜だということです。だからこそ今の段階で「身体を束ねるレイヤー」にポジションを取るプレイヤーが、その後のスケール期を支配し得るという構図が生まれています。2026年は、その勝負どころを各国・各企業が決める静かな分水嶺なのです。

地政学的な覇権争いとレイヤー戦略
世界経済フォーラムの報告によれば、生成AIブレイクスルー以降のヒューマノイド技術拠点は中国と米国に集中しており、notable foundation modelsの90%がこの両国発です[7]。さらにヒューマノイド関連の特許数は、中国が過去5年間で5,688件と世界最多で、米国の約4倍に達しています。
この状況で日本企業が「自前のヒューマノイド機体開発」を中心戦略に据えた場合、グローバル規模での量産・コスト競争に巻き込まれ、AIモデルやシミュレーション環境の標準が外部によって固まった後、その上に「載せてもらう」立場に固定されるリスクがあります。対して、既存の産業ロボット・製造業の現場知見とクラウド/エンタープライズAIの強みを活かし、NVIDIAスタックと早期統合してPhysical AIレイヤーを握りに行く戦略は、少なくとも勝ち筋の一つとして合理的でしょう。
さいごに
2026年のヒューマノイド元年とは、街に人型ロボットが溢れる「見た目の元年」ではなく、人間の行為がAPI化され、クラウドのエージェントAIが「身体を選べる」ようになる「構造の元年」として理解すべきです。重要なのは「どのロボットを買うか」ではなく、「どのような行為をAPIとして定義し、どのレイヤーに載せるか」を決めることです。
富士通のKozuchi Physical AI 1.0は、その物理レイヤーの標準ポジションを狙う日本発の挑戦です。2026年という分水嶺において、各企業は自社業務の「行為API化」を前提にアーキテクチャを描くことから始めるべきでしょう。身体は後から変えられますが、業務フローのAPI設計は簡単には変えられません。今、投資レバレッジが最も高いのは、まさにこのレイヤー戦略なのです。
出典
- [1] What is Physical AI? – NVIDIA Glossary
- [2] NVIDIA and US Manufacturing and Robotics Leaders Drive America’s Reindustrialization With Physical AI – NVIDIA Investor Relations
- [3] Accenture and Schaeffler Pave the Way for Industrial Humanoid Robots with NVIDIA and Microsoft Technologies – Accenture Newsroom
- [4] Fujitsu develops Fujitsu Kozuchi Physical AI 1.0 for seamless integration of physical and agentic AI / Physical AIやAIエージェントをシームレスに連携させる『Fujitsu Kozuchi Physical AI 1.0』を開発 – Fujitsu Global Newsroom / Press Room
- [5] Predictions 2026 – The Year of Embedded Intelligence – Fujitsu Corporate Blog
- [6] Humanoid robot: The AI accelerant – Goldman Sachs Research
- [7] Humanoid robots offer both disruption and promise. Here’s why – World Economic Forum