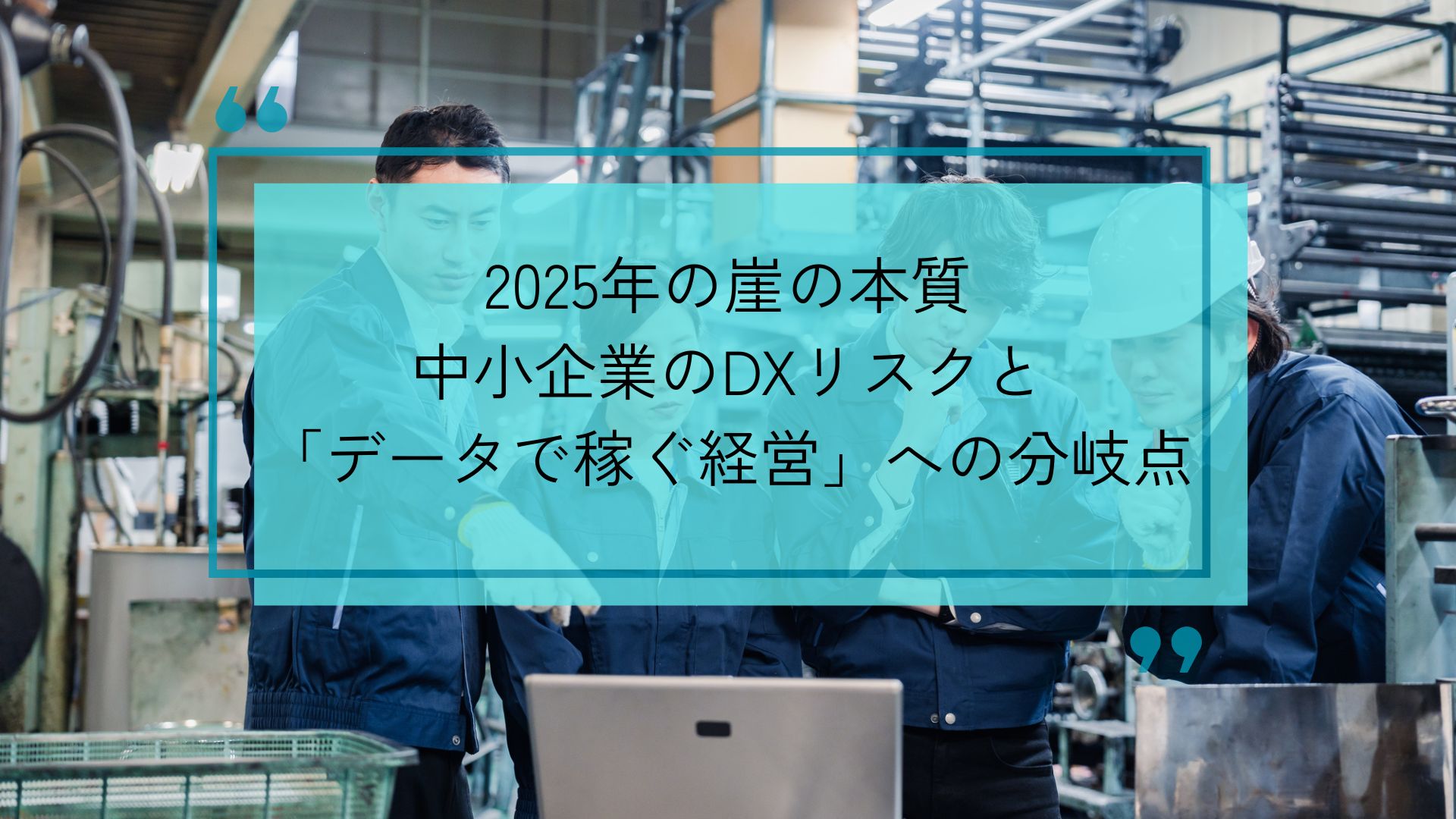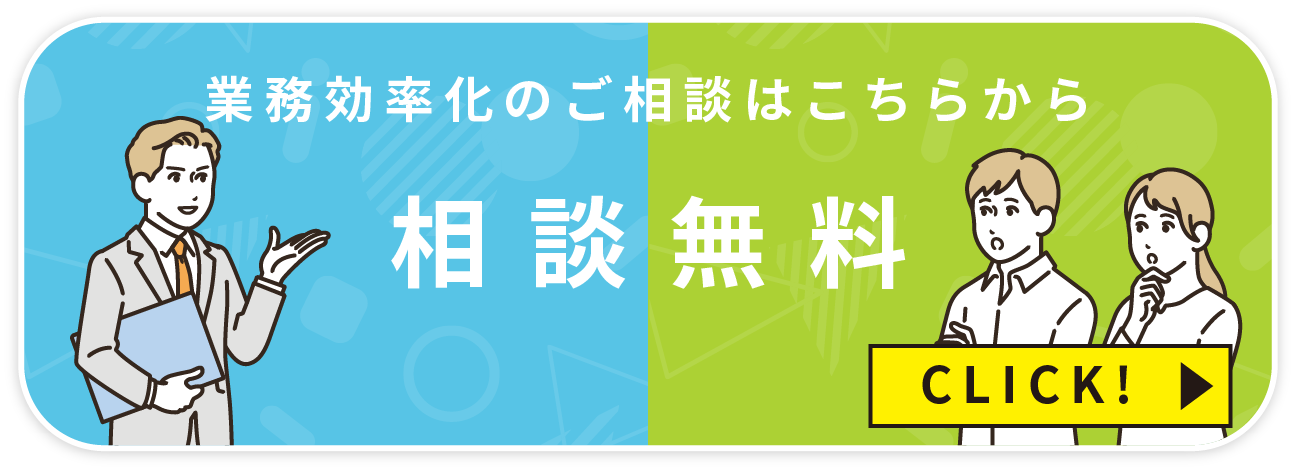「2025年の崖」という言葉を、あなたはどう受け止めているでしょうか。古いシステムが壊れるリスク、サポート終了による混乱、IT人材の不足――確かにそれらは現実の課題です。しかし、中小企業にとって本当に恐れるべきは、もっと静かで、もっと根深い変化かもしれません。それは「データで稼ぐ経営」に踏み出せない企業が、取引先と人材を少しずつ失っていく分岐点なのです。
「2025年の崖」とは何だったのか
経産省が示した12兆円の経済損失
経済産業省が2018年に公表した「DXレポート」は、日本企業に大きな衝撃を与えました。老朽化した基幹システムの維持費高騰、IT人材の高齢化、複雑化したシステムのブラックボックス化――これらが解消されないまま2025年以降に突入すれば、最大で年間12兆円規模の経済損失が生じうると試算されたのです[1]。この転換点が「2025年の崖」と名づけられ、以降DX推進の象徴的なキーワードとなりました。
ただし、ここで注意すべきは損失の中身です。システム障害による直接的な被害よりも、市場や顧客ニーズがデジタル技術を前提に動いていく中で、ついていけない企業が取りこぼす機会損失こそが問題の本質でした[1]。つまり、崖から落ちるのはシステムではなく、企業の競争力そのものだったのです。

DXへの取り組みは増えたが、成果は限定的
その後、IPA(情報処理推進機構)は「DX動向」シリーズを通じて、日本企業のDX状況を継続的に調査してきました。2024年版の分析によれば、「DXに取り組んでいる」と回答する企業の割合は年々増加しています。一方で、新たな製品やサービスの創出、ビジネスモデルの変革といった上位の成果に結びついている企業は限られているのが実情です[2]。
特に中堅企業を対象にしたディスカッションペーパーでは、DXの取り組みが業務プロセスの効率化に偏りがちで、「データで稼ぐ」という次元には到達していないことが明らかにされました。戦略を立てて全社を統括する人材、現場でDXを推進・実行する人材の不足、組織文化や働き方の硬直性がボトルネックになっているのです[3]。
中小企業が直面する本当のリスク
「古いシステム」ではなく「古い前提」が問題
多くの中小企業では、「2025年の崖」を「古いシステムを入れ替えないと危ない」というIT部門の問題として捉えがちです。しかし、それは表面的な理解に過ぎません。本質的な問題は、経営の前提そのものにあります。「ITは業務コスト削減の道具」「システムは壊さずに長く使うべき」「データは残っていると役立つかもしれない記録」――こうした前提が変わらない限り、システムを新しくしても同じような「新レガシー」をつくるだけです。
IPAの調査が示すように、日本企業の多くがDXを業務効率化に閉じ込めているのは、この古い前提を引きずっているからに他なりません[2]。特に中小企業では、リソースが限られるがゆえに「まずは効率化から」という発想にとどまりやすく、結果としてデータを武器にする発想への転換が遅れているのです。
取引と人材が静かに流出する構造
中小企業にとってより深刻なのは、大企業やプラットフォーマーがサプライチェーンや取引関係そのものをデジタル前提に作り替えつつあることです。需要予測や在庫最適化をサプライヤーのデータと連携して行う、生産・物流の状況をリアルタイムに共有する、顧客接点のオンライン化を通じて継続収益モデルに移行する――こうした動きは既に進行中です[2]。
この世界では、「データを出せるか」と「システム同士がつながるか」が取引条件そのものになります。基幹システムが古くて外部とAPI連携できない、生産や在庫のデータがリアルタイムに取れない、顧客との接点が紙と電話のまま――こうした状態に留まると、大手取引先のデータ前提のスキームに参加できず、見積・納期回答のスピードと精度で見劣りし、価格でしか勝負できなくなります。さらに「データを扱える環境」を求める若手人材から見て、魅力のない職場に映ってしまうのです。

IT人材不足が生む二重の赤字
DXレポートやIPAの調査が繰り返し指摘するように、日本は構造的なIT人材不足に直面しています。2025年におけるIT人材不足は最大約43万人規模に達しうるとされています[1]。この不足は中小企業にとって二重の痛手です。まず、レガシーシステムの維持に人を取られ、旧来の開発言語や独自仕様に精通した人材が少なくなる中で保守だけで手一杯になります。その結果、変革を担う人材に回す余力がなくなり、データ分析やサービス企画に人を割けず、「データで稼ぐ」方向の試行錯誤が進まないのです。
システムを守る人を確保すること自体が経営課題になってしまい、攻めのDXに人も予算も割けなくなる――これが、IT人材不足が「崖」の傾斜を急にする理由です。レガシーシステムモダン化委員会の設置など、国も対策を進めていますが[4]、中小企業が自社の状況に応じて優先順位を決め、限られたリソースを戦略的に配分する力が問われています。
「データで稼ぐ経営」への転換
DXの本丸は効率化ではない
経産省DXレポートが掲げたDXの定義は、単なるIT化ではありません。デジタル技術を活用して顧客や社会のニーズに応え、ビジネスモデルや企業文化を変革し、競争上の優位性を確立することです[1]。この定義を中小企業に引きつけて言い換えるなら、DXとは「データで稼ぐ構造」をつくることに他なりません。
顧客データ、利用状況や稼働状況のデータ、生産・在庫・品質データ、サービス利用のログ――こうしたデータを新しいサービスや課金方法、差別化要因に結晶させることこそがDXの本丸です。IPAの調査が示すように、日本企業の多くはまだこの本丸に届いていません[2]。多くが「業務プロセスの効率化」段階におり、「データで稼ぐ構造」づくりに至っていない――このギャップが、そのまま「崖」の高さになっているのです。

小さく始めて本丸を外さない
では、中小企業はどこから手をつけるべきでしょうか。すべての業務やすべての部門を一度に変えるのは現実的ではありません。むしろ、「この顧客(あるいはこの製品・サービス)について、どんなデータを集めれば、どんな稼ぎ方ができるか」というストーリーを一つだけ描いてみることが、DXの本丸への最短ルートです。
例えば、機械の稼働データを収集して予防保全サービスを提供する、顧客の購買履歴から次回提案の精度を高める、製造工程のデータを分析して品質保証の付加価値をつける――具体的なストーリーは業種や顧客によって異なります。重要なのは、「データで稼ぐ」という視点を経営の中心に据え、IT投資を「コスト削減の道具」ではなく「収益構造をつくるための前払い」として捉え直すことです。
レガシー対応の優先順位を変える
どのシステムから手をつけるかを「古さ」や「技術リスク」だけで決めると、再び”守りのIT”に閉じ込められます。そうではなく、「どのシステムが主要取引先とのデータ連携に最も影響するか」「どのシステムが若手人材から見た職場の魅力に最も影響するか」という観点で優先順位をつけるべきです。これは、崖の正体が「取引と人材の静かな流出」であるという本質から自然に導かれる発想です。
IPAのディスカッションペーパーが指摘するように、中堅・中小企業で不足しているのはDXの戦略を立てて全体像を描く人材です[3]。外部の専門家の力を借りることも一つの手ですが、最終的には経営者自身が「データで稼ぐストーリー」を描き、それを基準に投資判断を下す覚悟が求められます。
さいごに
「2025年の崖」は、古いシステムが壊れる技術的な崖ではありません。それは、データを前提とした取引・ビジネスに乗り遅れ、収益と人材が静かに流出していく経営上の崖です。レガシーシステム問題やIT人材不足は、あくまで「症状」であり、真のリスクはDXを「業務の効率化」に閉じ込めてしまい、データを使った収益機会の創出に経営として踏み込めないことにあります。
幸いなことに、この崖は突然やって来るものではありません。取引先との関係、若手人材の反応、市場での立ち位置――日々の経営の中に兆候は現れています。今からでも、一つの収益ストーリーをデータで描き、IT投資の位置づけを変え、レガシー対応の優先順位を「取引と人材」の観点で見直すことで、分岐点を正しい方向に進むことができます。「データで稼ぐ経営」への転換は、中小企業にこそ求められている決断なのです。
出典
- [1] DXレポート ― ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開 – 経済産業省
- [2] DX動向|企業等におけるDX推進状況調査分析 – IPA(情報処理推進機構)
- [3] DX動向2024 – 中堅企業のDXの取組についての考察 – IPA
- [4] レガシーシステムモダン化委員会設置に関する報道発表 – 経済産業省