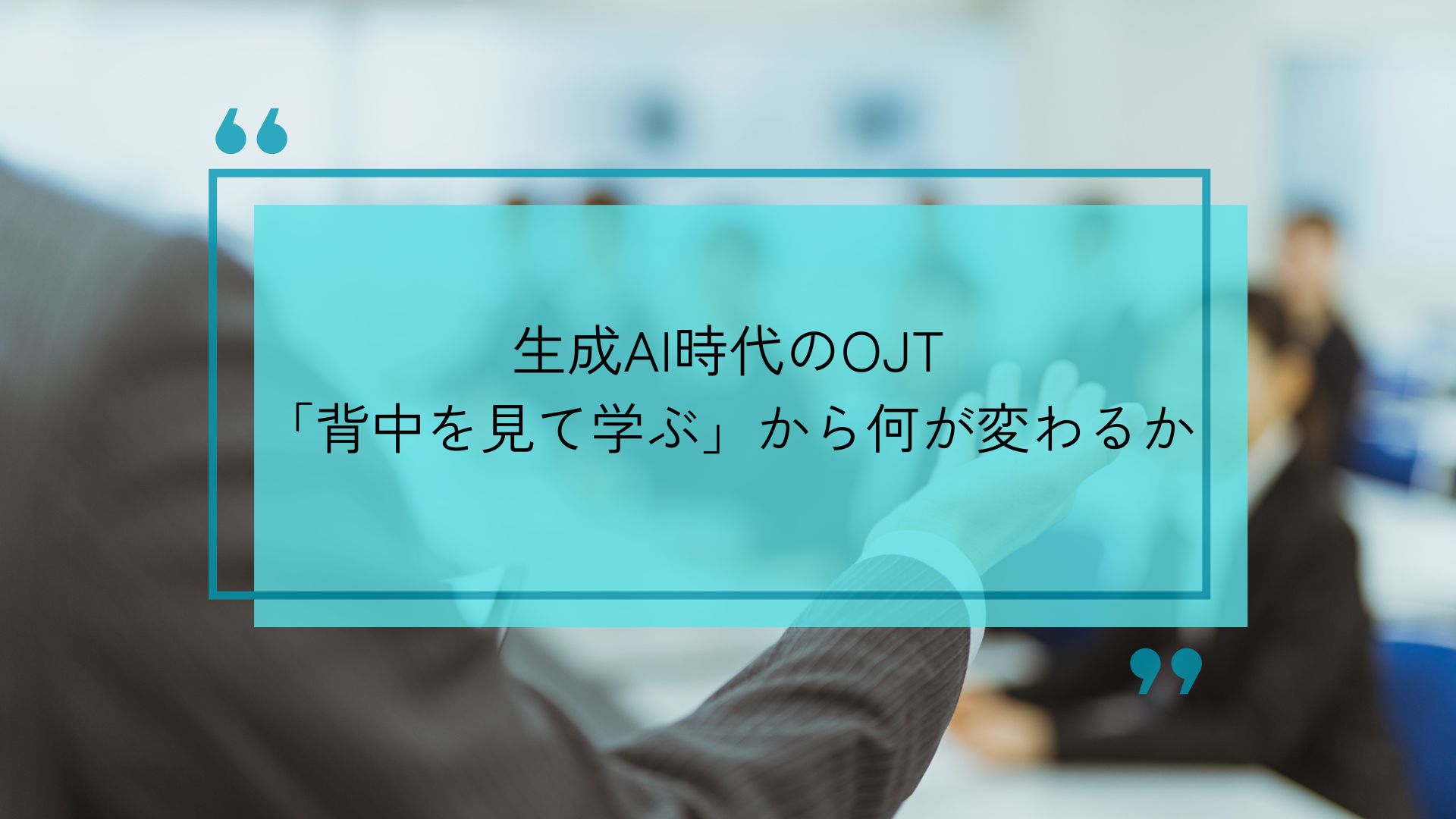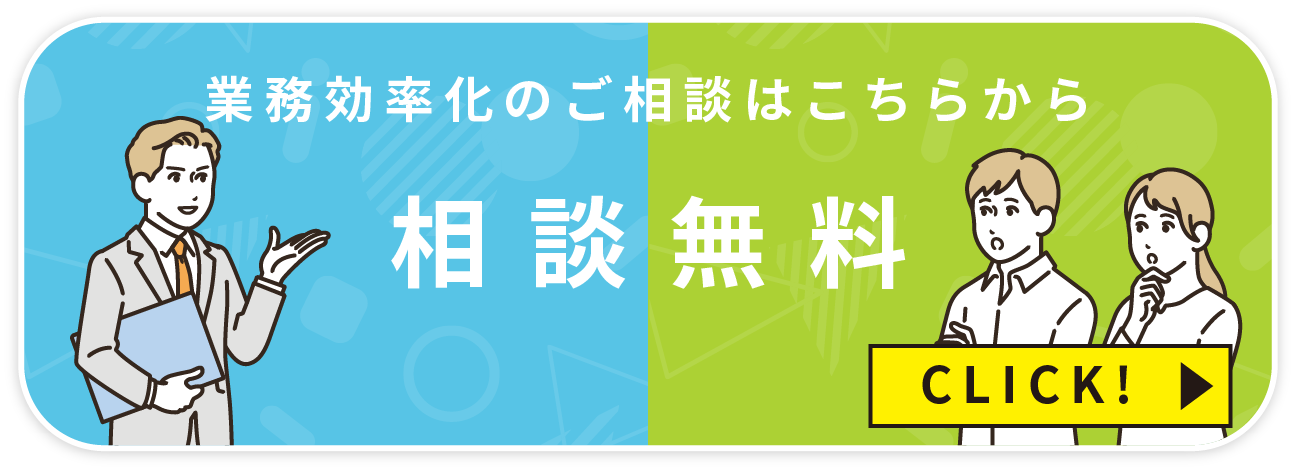生成AIが職場に浸透し始めた今、新人育成の現場で静かな混乱が起きています。かつて「先輩の背中を見て学べ」と言われた仕事の多くが、プロンプト一つで形になる時代です。
しかし、AIを使いたいと考える新入社員の86.7%に対し、実際に業務で活用している若手社員はわずか3割程度という現実があります[1][2]。このギャップを埋める鍵は、OJTそのものの再定義にあるのではないでしょうか。

世界と日本で広がる「AI活用」と「AI教育」のギャップ
社員の方が先にAIを使い始めている現実
世界的に見ると、企業の準備が整う前に、現場の社員たちが独自に生成AIを使い始めています。知識労働者の75%がすでに仕事で生成AIを利用しており、そのうち46%は利用開始から6か月未満という急速な普及ぶりです[3]。
一方で、会社からAI研修を受けた人はわずか39%にとどまり、今年ジェネレーティブAI研修を提供する予定の企業は25%に過ぎません。さらに注目すべきは、AIユーザーの78%が会社支給ではないツールを持ち込んで使っている点です[3]。
このデータが示すのは、「使われているのに、教えられていない」という構造的なギャップです。社員は業務上の負荷や時間不足を背景に、AIを自力で使い始めています。しかし企業側は、AIを前提とした業務設計や育成設計を十分に用意できていません。この世界共通の課題は、日本の「OJT依存の新人育成文化」と重なることで、より深刻な意味を持つようになっています。
日本の新人が抱える「意欲と実態」の矛盾
日本の新入社員に目を向けると、興味深い矛盾が浮かび上がります。2024年度の新入社員調査では、約86.7%が「今後、仕事で生成AIを活用していきたい」と回答しており、AI活用への意欲は決して低くありません[1]。ところが、東京都在住の20代若手社員400名を対象にした調査では、「まったく活用していない」が45.5%、「ほとんど活用していない」が26.0%と、合わせて約7割が実際にはほぼ使えていない状況が明らかになりました[2]。
活用していない理由として上位に挙がったのは、「現在の業務では活用する機会がない」(23.8%)、「使い方がよく分からない」(20.3%)、「会社がAIツールを導入していないため使えない」(20.2%)といった項目です[2]。つまり、本人の意欲の問題ではなく、環境と支援の欠如が障壁となっているのです。さらに、「今後、仕事でAIをどう活用していきたいか」という問いに対して「分からない」と答えた割合が36.3%で最多という結果も、新人たちの戸惑いを物語っています[2]。

OJTの構造的課題とAI時代に求められる変化
属人的で体系化されていない日本のOJT
日本企業のOJT実態を調べた調査では、417名の人事・人材開発担当者の多くがOJT教育に課題を感じており、トレーナー側の育成スキル不足や負担感、計画性の欠如などを問題視していることが分かりました[4]。従来のOJTは、現場の先輩社員の善意と経験則に大きく依存してきましたが、その属人性ゆえに、新しい技術環境への適応が遅れているのです。
さらにマクロな視点では、日本企業は人材投資が不十分であり、個人も自ら学ぼうとしない傾向が強く、その間にデジタルスキルギャップが拡大していると指摘されています[5]。生成AI時代においては、座学中心の人材育成だけでなく、実際の業務の中で学び続ける「ラーニング・イン・ザ・フロー・オブ・ワーク」が不可欠です[6]。しかし現状のOJTは、生成AIという仕事のやり方を変える技術を、新人の学びに変換する仕組みとして機能していません。
AIが変えるのは「手順」ではなく「手順を覚える意味」
生成AIによって、必要とされるスキル構成が加速的に変化しています。知識そのものや定型的な手順の価値は相対的に下がり、課題設定、批判的思考、コミュニケーション、倫理的判断といった、AIが代替しにくいスキルの重要性が高まっていると言われています[6]。AIパワーユーザーとそうでないユーザーを比較すると、パワーユーザーはAIにどう聞くかを試行錯誤し、仕事のプロセスそのものをAI前提で再設計し、AIの出力を批判的に検証しながら活用しています[3]。
その結果、パワーユーザーは一日のうち30分以上の時間を節約し、創造性や仕事へのモチベーションが大きく向上しています[3]。つまり、「AIが手順を代わりにやってくれる」世界では、手順そのものを覚えることよりも、「そもそも何を頼むべきか」「出てきた結果をどう評価するか」を学ぶことの方が、はるかに重要になるのです。
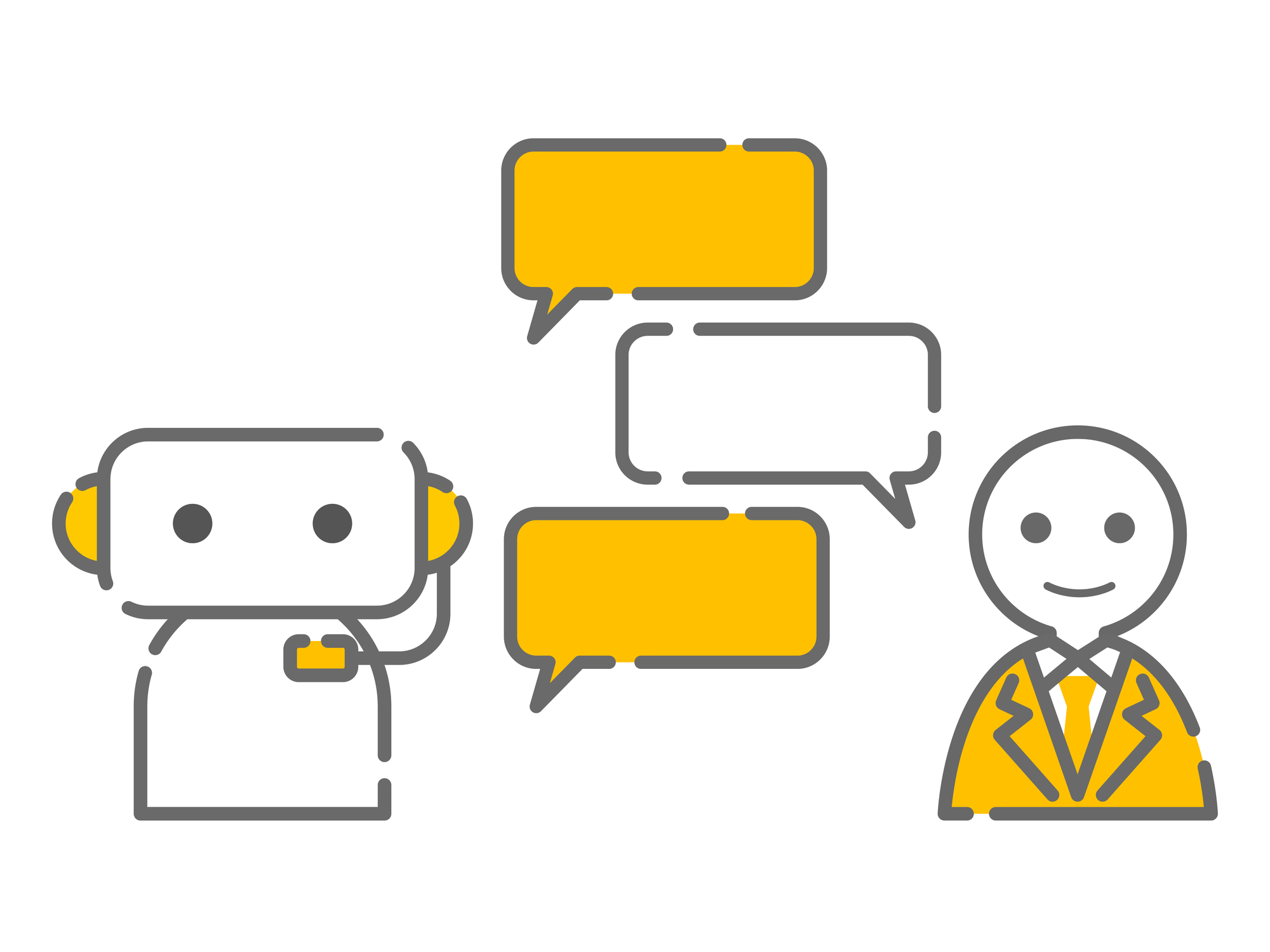
「教える」から「問いとレビューで返す」へ
現場でしか学べないスキルになった
「AIに何を頼み、どう評価するか」というスキルは、座学だけでは身に付きません。実際の自社データ、自社の顧客、自社の商習慣や倫理基準といったコンテキストの中で、「これはAIに任せていい」「これは自分で判断すべき」「このグレーゾーンは先輩に相談すべき」といった線引きを、具体的な仕事を通じて経験する必要があります。従来のOJTが「この仕事はこうやる」というやり方を先輩が口頭や赤入れで教える場だったとすれば、生成AI時代のOJTは「この仕事は、どこまでAIに任せていいか」「そのとき何を入力すべきか」「AIの出力のどこを疑うべきか」を、新人と一緒に考え、試し、レビューする場へと変わる必要があります。
この転換を実現するには、OJTトレーナーの役割を根本的に再定義することが求められます。先輩は「答えを持っている人」ではなく、「良い問いを投げ、新人にAIとともに考えさせる人」「AIと新人が出した成果物に対し、判断基準とレビューを提供する人」として位置づけられるべきです。そうすることで、新人は早期に「判断と責任」の領域にアクセスでき、AIへの正しい頼り方と怖がり方を同時に身につけることができます。
「新人×AI×先輩」の三者サイクルを回す
具体的には、1on1やOJT面談で「AIをどう使ったか」「どこまで任せたか」「どこで不安を感じたか」を必ず題材にし、レビューの場では成果物の完成度だけでなく、「AIへの指示・プロンプト」と「AIの結果に対する判断」を一緒に振り返ることが重要です。このサイクルを回すことで、新人の学習速度は飛躍的に高まり、先輩自身もAI前提で仕事を再定義する機会を得られます。ただし、トレーナー側にAI活用リテラシーがない場合は形骸化するリスクがあり、AIへの過度な依存を助長しないよう、「どこからが自分の責任か」を明確に線引きするルール作りも並行して必要です。
一部には「まずはAI抜きで仕事の型を身に付けさせるべき」という意見もあるでしょう。確かに、AIに頼らなくても基礎スキルを身につけられるメリットはあります。しかし、学習負荷が高く立ち上がりに時間がかかること、実務ではすでにAIが前提になりつつある領域で旧来のやり方を学ばせる非効率を考えると、現実的かつ将来志向の選択肢とは言えません。
さいごに
生成AI時代のOJTの成否は、「正しいやり方を教える量」ではなく、「新人がAIと組んで自分で答えをつくり、先輩が問いとレビューで返すサイクルの質」にシフトしていくでしょう。世界では社員の方が先にAIを使い始め、企業の準備が追いついていません。日本の新人たちはAIを使いたいのに、使い方も使う場面も分からず戸惑っています。この状況を打開するのは、座学研修ではなく、現場での実践とフィードバックの場、すなわちOJTです。
「背中を見て学ぶ」という言葉は、これからも大切な教えであり続けるでしょう。ただし、その「背中」が示すものが変わるのです。手順を黙々とこなす背中ではなく、AIと対話しながら試行錯誤し、判断し、責任を引き受ける背中。そんな新しい背中を、先輩たちが新人に見せられるかどうかが、これからの育成の鍵となるはずです。
出典
- [1] 新入社員の会社生活調査 2025 – 産業能率大学 総合研究所
- [2] 【Z世代意識調査】若手社員の7割が生成AI『活用していない』、今後の活用イメージも『わからない』が1位に – リ・カレント株式会社
- [3] AI at Work Is Here. Now Comes the Hard Part – 2024 Work Trend Index Annual Report – Microsoft & LinkedIn
- [4] OJTの実施状況と課題 実態調査レポート – アルー株式会社
- [5] Society 5.0時代のデジタル人材育成に関する検討会 報告書 – 経済産業省
- [6] 生成 AI 時代の DX 推進に必要な人材・スキルの考え方 – 経済産業省