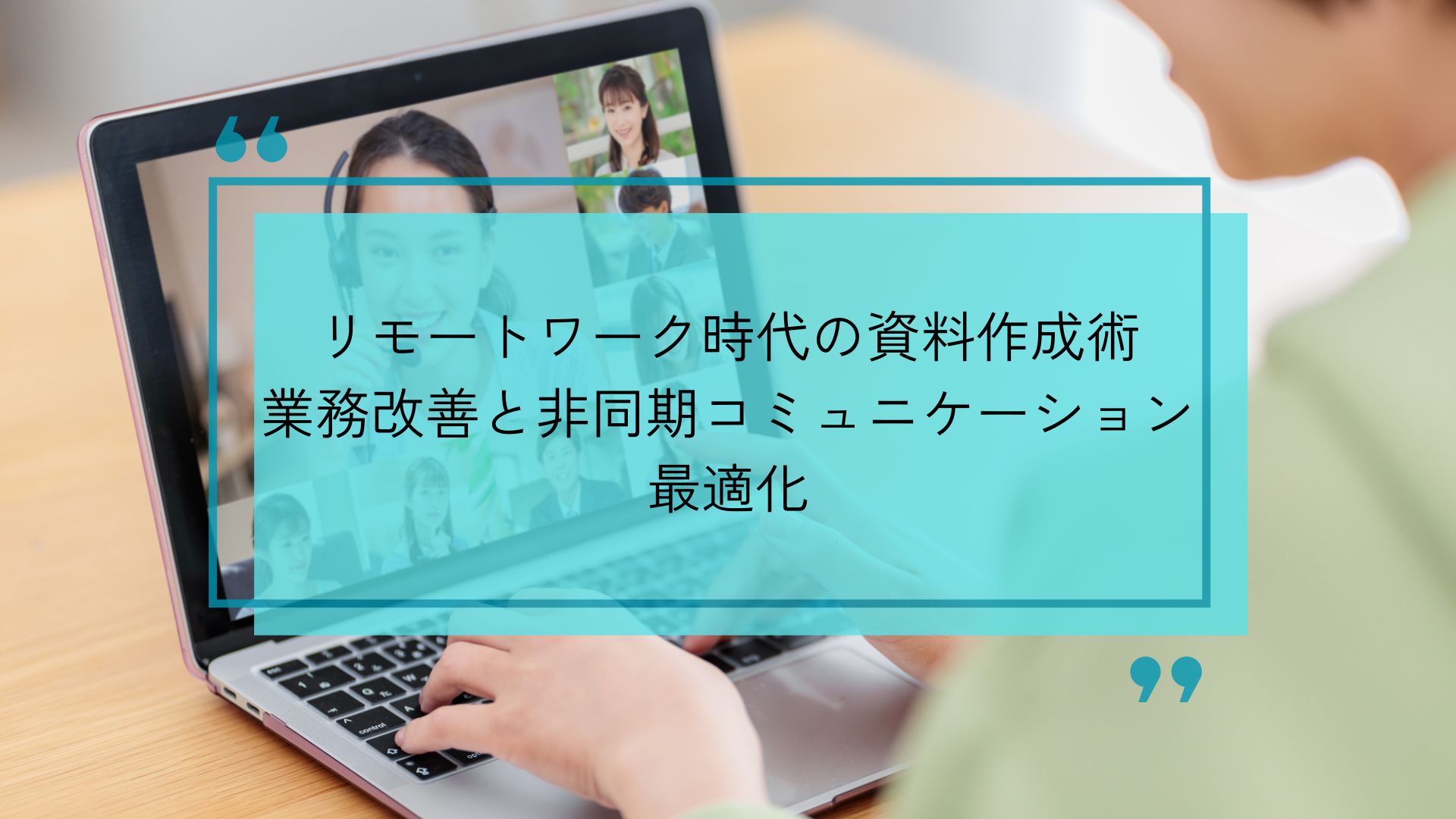コロナ禍以降、リモートワークは多くの企業で定着しつつあります。しかし、緊急導入から数年が経過した現在、業務改善の必要性が改めて問われています。特に資料作成においては、対面での気軽な確認ができない環境下で、いかに効率よく情報を伝えるかが重要な課題となっています。本記事では、リモートワーク環境における資料作成術と、業務改善のポイントを具体的に解説します。
リモートワークにおける資料作成の基本と業務改善ポイント
非同期コミュニケーションで成果を出すための資料作成術
リモートワークでは、同じ時間に全員が揃って作業できるとは限りません。そのため、非同期コミュニケーションを前提とした資料作成が求められます。まず重要なのは、資料単体で完結する情報設計です。背景や目的、期待する行動まで明確に記載することで、受け手が適切なタイミングで理解し、対応できるようになります。

次に、情報の一元管理が欠かせません。情報共有ツールを導入することで、バラバラに散在していたドキュメントを一元管理することができ、「どこに情報があるか分からない」「あの人しか知らない」といった属人化問題が大きく改善されます。資料作成時には、誰もがアクセスできる共有スペースに保存し、ファイル名や分類ルールを統一することが業務改善の第一歩となります。
リモートワーク下で効率化する業務改善のコツ
業務改善を進めるには、資料作成のテンプレート化が有効です。議事録、提案書、報告書など、頻繁に作成する資料の型を用意しておくことで、作成時間を大幅に短縮できます。また、テンプレートがあることで、誰が作成しても一定の品質が保たれ、情報の抜け漏れも防げます。
さらに、定期的な資料の棚卸しも重要です。古い情報や更新されていないドキュメントは、かえって混乱を招きます。四半期ごとなど、定期的に不要な資料を整理し、最新情報を維持することで、リモートワーク環境でも円滑な業務遂行が可能になります。
リモートワークの作業効率を最大化する方法
作業効率化のためのツール選定と活用
作業効率を高めるには、適切なツール選定が不可欠です。文書共有にはクラウドストレージ、タスク管理にはプロジェクト管理ツール、コミュニケーションにはチャットツールと、用途に応じて使い分けることが重要です。ツールを選ぶ際は、操作性の良さとセキュリティのバランスを考慮しましょう。特に非IT部門の社員でも使いやすい操作性は、全社的な定着に直結します。
興味深いのは、テレワークの効率性に関する経年変化です。2020年6月時点と2023年7月時点を比較すると、テレワーク実施者が「仕事の効率が向上した」と感じる割合が増加しており、慣れや環境整備によって生産性が上昇していることが確認されています[1]。これは、ツールの習熟と業務プロセスの最適化が進んだ結果と言えるでしょう。
管理・進捗の可視化で課題を早期発見
リモートワークでは、メンバーの作業状況が見えにくくなります。そこで、進捗の可視化が業務改善の鍵となります。タスク管理ツールを使って、誰が何をいつまでに行うのかを明確にし、進捗状況をリアルタイムで共有しましょう。これにより、遅延やボトルネックを早期に発見でき、迅速な対応が可能になります。
また、定期的な振り返りの場を設けることも効果的です。週次や月次で進捗を確認し、課題を洗い出すことで、継続的な業務改善につながります。ただし、過度な管理は信頼関係を損ねる可能性があるため、メンバーの自律性を尊重するバランス感覚が求められます。
リモートワーク業務改善に役立つコミュニケーション手法
チャット・Web会議を活かした情報共有の工夫
チャットツールは即時性が高い一方、情報が流れやすいという特性があります。重要な決定事項や参照すべき情報は、チャットだけでなくドキュメント管理ツールにも記録しておくことが重要です。一方、Web会議は対面に近いコミュニケーションが可能ですが、時間的制約もあります。定例会議は短時間で効率的に行い、詳細な議論が必要な場合は別途時間を設けるなど、目的に応じて使い分けましょう。

また、情報共有の際は「誰に何を伝えるべきか」を明確にすることが大切です。全員に一斉送信するのではなく、関係者を適切に選定することで、情報過多を防ぎ、受け手の負担を軽減できます。
よくある課題と解決策の成功事例
リモートワークでよく聞かれる課題が「情報の属人化」です。特定の担当者しか知らない情報があると、その人が不在の際に業務が滞ります。この課題に対しては、情報共有ツールの全文検索機能が有効です。教育や業務引き継ぎの負担と時間が短縮され、新人教育や業務継承時の効率が大幅に向上されることが期待できます。
また、「気軽に質問できない」という心理的なハードルも課題となります。これに対しては、質問専用のチャンネルを設けたり、定期的な雑談の時間を設けたりすることで、コミュニケーションの心理的障壁を下げる工夫が効果的です。
資料作成時に意識すべきリスクとセキュリティ対策
情報漏洩を防ぐための実践的ポイント
リモートワークにおけるセキュリティリスクは深刻です。2021年度の調査によると、コロナ禍の緊急導入時に認められた例外的な特別措置(機密情報を含むUSBメモリや会社支給PCの持ち出し、個人PCでの機密情報保存など)が長期化・常態化している企業が多数確認されています[2]。こうした例外対応の継続は、情報漏洩などのセキュリティリスクを高める要因となります。

資料作成時には、機密レベルに応じたアクセス権限の設定や、クラウドサービスのセキュリティ機能を活用することが重要です。また、個人デバイスでの業務を避け、会社支給の端末を使用する、VPN接続を徹底するなど、基本的なセキュリティ対策を怠らないようにしましょう。
モチベーション低下やコミュニケーション障害への対応
リモートワークの長期化に伴い、孤独感やモチベーション低下といった心理的な課題も顕在化しています。資料作成においても、孤独に作業を進めるのではなく、適度にフィードバックを求めたり、進捗を共有したりすることで、チームとのつながりを維持することが大切です。
また、文字だけのコミュニケーションは誤解を招きやすいため、意図が伝わりにくい場合は、ビデオ通話で直接説明するなど、柔軟に手段を変えることも必要です。相手の反応が見えにくいからこそ、丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。
生産性向上を実現する評価制度とフィードバックの活用法
最新の人事評価基準とリモートワーク適応法
リモートワークにおける人事評価は、成果主義への移行が進んでいます。従来の「働いている姿勢」よりも、「何を達成したか」が重視されるようになっています。評価基準を明確にし、定期的に進捗を確認することで、メンバーは安心して業務に取り組めます。
また、評価面談もオンラインで実施する企業が増えています。対面と比べて緊張が和らぐというメリットもありますが、一方で非言語コミュニケーションが伝わりにくいため、より丁寧な言葉選びや、具体的なフィードバックが求められます。
業務改善マニュアルの作り方と継続的な成果向上
業務改善を継続的に進めるには、改善事例やノウハウを蓄積することが重要です。マニュアル作成時には、単なる手順書ではなく、「なぜそうするのか」という背景や意図も記載しましょう。これにより、状況が変わった際にも応用が利きやすくなります。
また、マニュアルは一度作って終わりではありません。定期的に見直し、現場の声を反映してアップデートすることで、実用性の高いドキュメントとして育てていくことが大切です。バージョン管理機能を活用すれば、変更履歴も追跡でき、改善の経緯を振り返ることも可能になります
。
おすすめのリモートワークツール・グッズ比較
コストパフォーマンスに優れたリモートワークツール
ツール選定では、機能性とコストのバランスが重要です。無料プランでも十分な機能を提供するツールも多く、まずは小規模で試験導入してから本格展開するのが賢明です。特に、ファイル内全文検索やバージョン管理のしやすさ、強固なセキュリティ設計は、長期的な運用において重要な判断基準となります。
また、既存システムとの連携性も考慮すべきポイントです。単体では優れていても、他のツールと連携できなければ、かえって業務が煩雑になる可能性があります。
長時間労働を防ぎ健康を守るアイテム
リモートワークでは、通勤時間がなくなる一方で、仕事とプライベートの境界が曖昧になりがちです。健康を守るためには、デスク環境の整備が欠かせません。エルゴノミクスに基づいた椅子やデスク、ブルーライトカットメガネなど、長時間の作業でも疲労を軽減できるグッズを活用しましょう。
また、定期的な休憩を促すタイマーアプリや、運動を習慣化するウェアラブルデバイスも、健康維持に役立ちます。体調管理は生産性の基盤であることを忘れずに、適切な投資を行いましょう。
まとめ
リモートワーク環境における資料作成と業務改善は、非同期コミュニケーションを前提とした情報設計と、適切なツール活用が鍵となります。2020年の緊急導入時には全国でテレワーク利用率が25%まで上昇しましたが、2023年3月時点では13%まで低下しており[1]、定着には継続的な工夫が必要です。
一方で、テレワークに慣れた実施者の間では効率性が向上しているというデータもあり[1]、環境整備と業務プロセスの最適化によって、リモートワークでも高い生産性を実現できることが示されています。情報の一元管理、セキュリティ対策の徹底、適切なコミュニケーション手法の選択を通じて、リモートワーク時代にふさわしい働き方を構築していきましょう。
まずは小さな改善から始め、継続的にブラッシュアップしていくことが、長期的な成果につながります。
出典
- [1] 第166回「テレワークが減少している」 – 経済産業研究所 (RIETI)
- [2] 企業・組織におけるテレワークのセキュリティ実態調査 – IPA(情報処理推進機構)